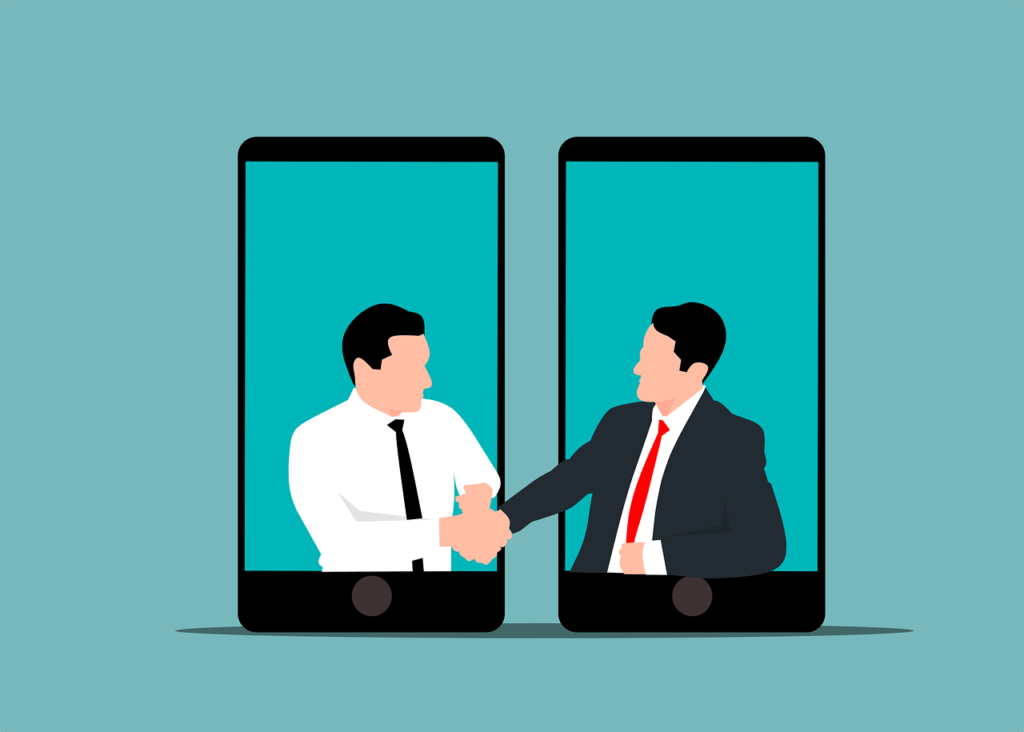
今回は株式会社設立の定款作成・認証から設立登記までの流れとその必要な費用について語っていきたいと思います。
冒頭に、設立登記を依頼する場合は司法書士さんにしか依頼できないという事を憶えておいてください。
では定款作成・認証から設立までの流れをご紹介します。
定款作成
まず、会社を設立するにあたり定款を作成して公証人に認証してもらう必要があります。
この定款とは、わかりやすく言ってしまうと会社版の憲法です。
定款は『絶対的記載事項』と『相対的記載事項』と『任意的記載事項』の3つで構成されています。
絶対的記載事項
『絶対的記載事項』は定款に必ず記載しなければ公証人の認証を受けられない以下の5つの記載事項があります。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立の際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
相対的記載事項
『相対的記載事項』は記載しなければ効力を生じない事項です。
例えば、よくある記載事項として株式の譲渡制限に関する事項です。
会社の登記事項証明書に「株式の譲渡制限に関する規定:当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の決議による承認を受けなければならない。」などと記載されているのを見たことはないでしょうか。
株式の売買は民法上の売買契約に該当し債権契約の一種です。本来であれば債権は自由に譲渡できますが、株を保有している全ての株主が株式を自由に譲渡できてしまうと意図しない人物に株式が集まり、その意図しない人物に会社を支配されてしまいます。
そこで相対的記載事項によって株式の譲渡に制限をかけて、株主総会や取締役会などの承認がなければ譲渡による取得を認めないという効力を生じさせることができます。
任意的記載事項
『任意的記載事項』は上記の必ず記載しなければならない事項、記載しなければ効力を生じない事項以外の事項で、会社が記載するかどうかを自由に決められる事項です。
例えば、事業年度や取締役等の人数、株主総会の議長、などなど。
定款に記載する義務はありませんが定款で定めておけば会社内部のルールが明確化され会社組織の安定性を高められます。
プチ情報
ここで一つ!
使用できる商号かを調査し商号が決定したら代表印・会社の横判・会社の銀行印を作りましょう!
定款認証後の設立登記をするときには代表印(会社印)が必要になり、設立後は法人名義の預金通帳をつくることができるので会社の銀行印が必要となります。
認証
定款の作成が終わったら、印鑑登録証明書、表明保証書、実質的支配者となるべきものの申告書等々の書類を揃えて公証役場に定款認証の依頼をします。
定款認証を行うには『紙の定款』と『電子定款』2通りの認証方法があります。
紙の定款
定款を紙によって作成します。紙の定款の場合、公証役場保管用の定款と法務局への登記申請用の定款、そして会社保存用の定款の計3通の定款を作成し、公証役場へ持参して公証人に認証してもらうことになります。
電子定款
電子定款はPDFで作成した定款を電子認証したものをいいます。
PDFで作成した定款案をメールで公証人に事前確認をしてもらい、事前確認が完了したら電子署名をして法務省の申請用総合ソフトにてオンライン申請をします。そして認証日に必要書類を持参して公証役場に行き認証された電子定款を受け取ります。
電子定款のメリットとして紙の定款は収入印紙代で4万円の費用がかかりますが、電子定款は収入印紙代がかかりません。しかし、電子署名付きPDF変換ソフトや電子証明書の申請などの費用とその設定に時間がかかります。司法書士や行政書士のように年に何件かの定款認証業務をやっていればいいのですが、自身でたった1度の電子定款の申請をするとなると、たった1度の電子定款の申請をするがために電子署名付きPDF変換ソフトや電子証明書の費用と時間を費やすこととなるので、自身でやるより専門家に依頼することを強くお勧めします。
紙の定款と電子定款の比較
| 収入印紙代 | 定款認証手数料 | 作成方法 | 初期費用と時間 | メリット・デメリット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 『紙の定款』 | 4万円 | 3万円~ 5万円 | 紙 | かからない | 収入印紙代の4万円の費用がかかる |
| 『電子定款』 | 不要 | 3万円~ 5万円 | かかる | 収入印紙代は不要だが、電子署名付きPDFソフトや電子証明書などの初期費用と時間がかかる |
※定款認証手数料は資本金の額が
100万円未満・・・・・・・・・・3万円
100万円以上300万円未満・・・4万円
300万以上・・・・・・・・・・・5万円
◦収入印紙はコンビニや郵便局でも購入できます。
◦定款認証手数料は公証役場に支払います。
設立登記
定款認証が済んだらいよいよ設立登記となります。設立登記は冒頭でもお話ししましたが司法書士さんにしか依頼することができません。なのでここからは行政書士の私が司法書士さんに引き継ぎの際にお渡ししている設立登記に必要な書類をご紹介します。
私が司法書士の先生にお渡ししている書類
- 認証した定款と公証役場で受け取った書類
- 発起人決議書
- 就任承諾書
- 印鑑登録証明書
- 払込があったことを証する書面
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
払込があったことを証する書面は、払い込みをした通帳のコピーと一緒に綴じて代表印(会社印)を押印し、全ページに契印をします。
印鑑届書と印鑑カード交付申請書は代表印(会社印)の届出とその届け出た代表印の印鑑カードを交付する申請となるため代表印を押印します(印鑑届書の届出人又は委任状の委任者の印は提出者の実印の押印が必要)。
※定款作成の最後のところで触れてますが会社の商号が決まったらすぐに印鑑を作っておかないと、上記のように司法書士さんに引き継ぐ書類に押印しなければならないので、会社設立のスケジュールに余裕が無い場合、設立登記までに代表印(会社印)を用意できないと設立が遅れてしまいます。
以上の書類を司法書士さんに引き継いでいただいてます。
設立の日
ちなみに、設立登記の申請書を法務局が受理した日が、設立した日として登記されます。なのでたとえ休日にオンライン申請を行えたとしても、受理されるのは法務局が営業している日になり、休み明けの日付になってしまいます。官公庁の休日を設立日にすることはできません。1月1日や5月5日を設立日にしたいという方は今の時点では不可能です。また、自分の誕生日や記念日などを設立日にしたいという場合も、その日が官公庁の休日になってしまっているとその日を設立日とすることはできません。
設立登記の費用
登記をする際の登録免許税を法務局に納めなければなりません。
登録免許税は定款認証手数料同様に資本金の額によって変わってきます。
◦資本金の額の7/1000
◦資本金の額の7/1000が15万円に満たない場合は一律最低額15万円
分かりやすく説明すると・・・
◆資本金の額が5000万円
5000万円×7/1000=35万円
登録免許税35万円
◆資本金の額が1000万円
1000万円×7/1000=7万円
15万円に満たないので最低額の登録免許税で15万円
一応、一律最低額15万円のラインを前後する資本金の額を計算してみましょう。
15万円÷0.007=2142万8571円
資本金が約2150万円を超えてくると15万円以上になるイメージでいいと思います。
これにプラスして司法書士さんの報酬額が加算されます。
まとめ
手順としては定款案作成➡印鑑の注文➡定款の認証➡設立登記といった流れになります。
費用としては資本金1000万円として
◦『紙の定款』:収入印紙代4万円+定款認証手数料5万円+登録免許税15万円=計24万円
◦『電子定款』:収入印紙代0円+定款認証手数料5万円+登録免許税15万円=計20万円
電子定款を専門家に依頼した方が収入印紙の分の4万円安くなります。
ただし、自分で電子定款の認証をする場合は電子署名付きPDF変換ソフトや電子証明書の申請等に費用と時間を費やすこととなります。
また、専門家に依頼した場合は上記の実費の他に専門家に支払う報酬があります。
定款作成の報酬、定款認証の報酬、登記の報酬はご依頼された事務所にによって報酬額の設定が違ってくるので、一概にはこの値段!ということは言えませんが上記の実費に+13万円(税抜)~18万円(税抜)程度の報酬額がかかってくると思っていた方がよいでしょう。
私の個人的な見解となってしまいますが、法人の設立は専門家に依頼することをお勧めします。
理由は、設立登記までに作成していく書類に入れる日付の順序を間違えてしまうと何度も書類を作り直すさなければならなくなったりして、場合によっては登記申請も受け付けてもらえない可能性もあります。
また商法会社法をよく理解していない状態で定款の作成をしてしまうと、漏れや矛盾を生じてしまう可能性が高くなってきます。そうなった場合は設立後に臨時の株主総会を開き定款変更をしなければならなくなってしまい、後々とても面倒なことになってしまいます。
最後に
これから、会社を設立して経営していこうと考えている方!
会社の設立費用に気を取られて、いろいろと考える時間を費やしてしまいがちですが、お金がかかっても専門家に依頼をしてサクッと会社設立をして、設立した会社の事業運営に時間と労力を注いでもらえればと思います。
⇩ ⇩ ⇩
