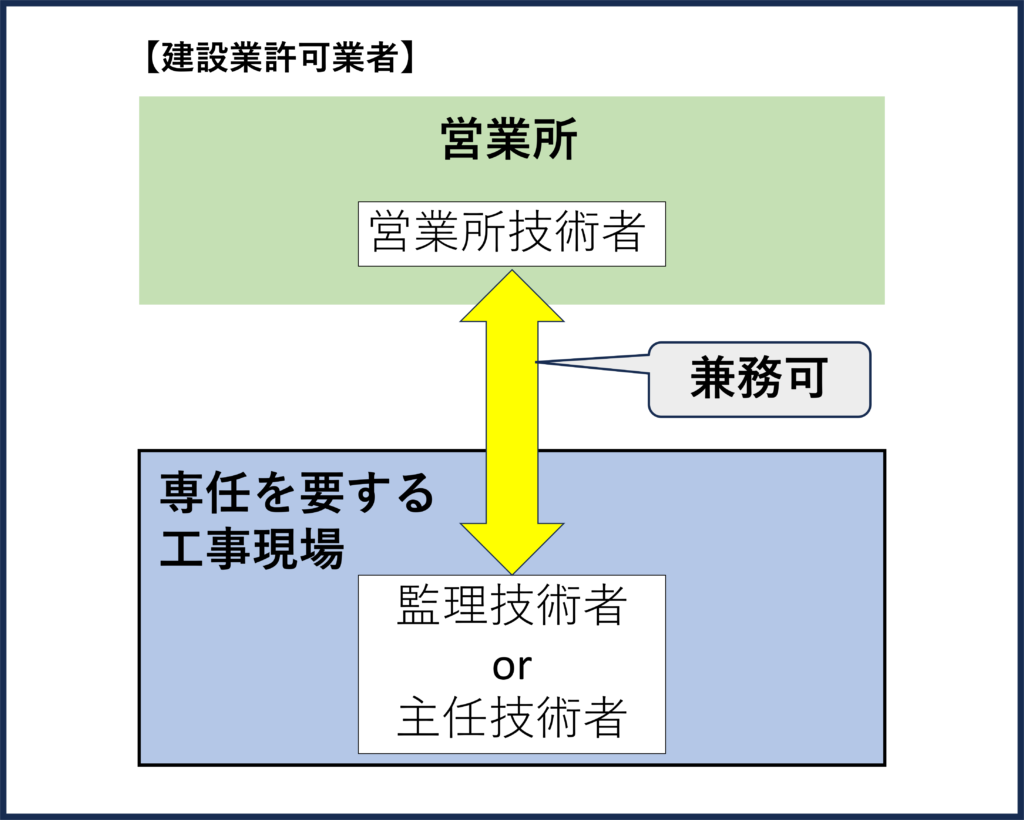建設業の許可要件を見る前に、なぜ建設業許可を受けた方がよいのかを「建設業許可はなぜ必要?」にメリット・デメリットと共に書いてあります。なぜ?と思われる方はまずは「建設業許可はなぜ必要?」を読んでみてください。
【建設業許可要件のリンク先】
建設業許可 要件 経営業務の管理責任者編
建設業許可 要件(営業所の専任技術者) 専任の技術者編
建設業許可 要件 500万円 財産的基礎等編
建設業許可 要件 欠格要件及び拒否事由編
〈建設業法第7条及び3号〉
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
建設業の性質上、注文生産により、取引の開始から終了まで長い期間を要することもあり、前渡金などの金銭のやりとりが習慣化しています。それは信用を前提として行われているということもあり、請負契約の締結やその履行に際して、不正又は不誠実な行為をするような業者は営業を認めてもらえません。
では「不正又は不誠実な行為」とはどういった事なのか解説していきたいと思います。
| ◇不正な行為と不誠実な行為 |
|---|
| ●「不正の行為」とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいいます。 【例】詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律に違反する行為 ●「不正実な行為」とは、請負契約に違反する行為をいいます。 【例】工事内容や工期などの、請負契約に違反する行為 ●申請者が法人である場合において当該法人の非常勤役員を含む役員等及び営業所の代表者(令第3条の使用人)が、又は申請者が個人である場合においてその者及び使用人(令第3条の使用人)が、次に該当する場合は誠実性を満たさないものとして取り扱われます。 【例】「宅地建物業法」の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者 ●許可を受けて継続して建設業を営んでいたものについては、「不正な行為」又は「不誠実な行為」に該当する行為を行った事実が確知された場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われます。 |
◇役員等
◦「役員等」とは
「業務を執行する社員」、「取締役」、「執行役」若しくは「これらに準ずる者」又は「相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者」をいいます。《建設業法第5条3号》
◦「業務を執行する社員」とは
持分会社の業務をしっこうする社員をいいます。
◦「取締役」とは
株式会社の取締役をいいます。
◦「執行役」とは
指名委員会等設置会社の執行役をいいます。
◦「これらに準ずる者」とは
法人格のある各種の組合等の理事をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事等は原則含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等を含みます。
◦「相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者」とは
少なくとも相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。いか「株主等」という)、このほか、名称役職の以下を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。
◦「役員等」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含まれません。
少し、建設業許可要件の1つ「欠格要件」に似た部分もありましたね。
建設業許可を取得、若しくは維持をしていくためには、不誠実な行為も許されないということです。
今回は以上です。「欠格要件」のリンクも貼っておきますので、参考までに覗いてみてください。
リンク「欠格要件」
⇩ ⇩ ⇩