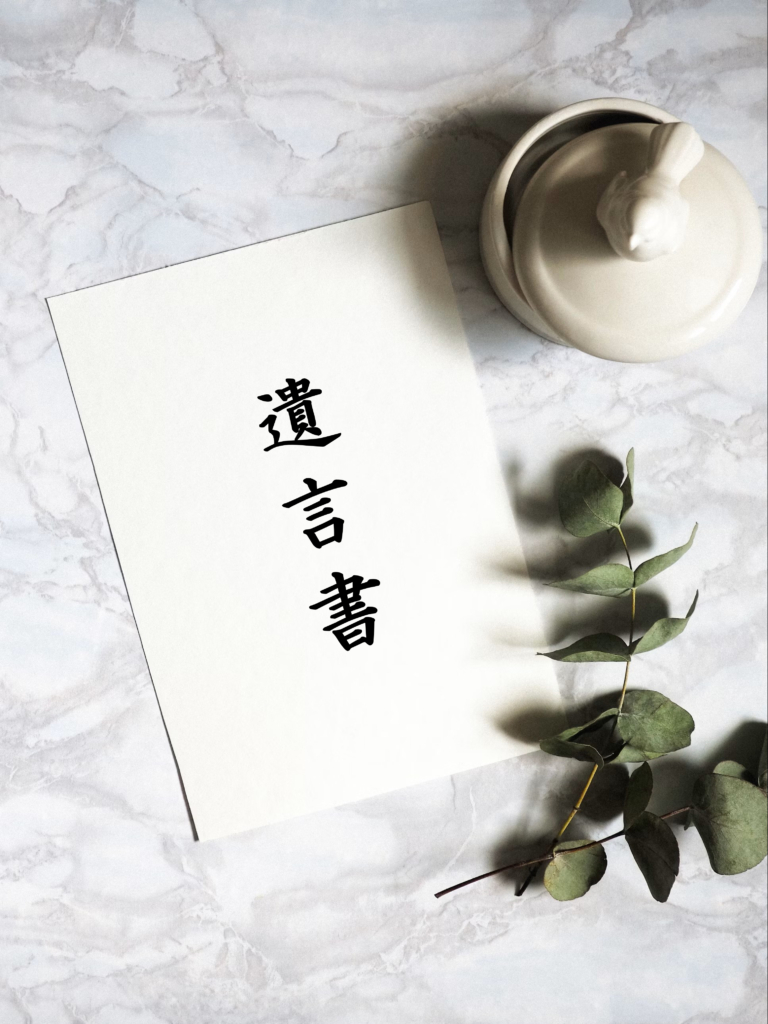
はしめに
以前、「遺言書 書くべき人」というタイトルでブログを書かせていただきました。今回は遺言書を作成したいけど、どの種類の遺言書を作成すればいいの?と思っている人向けに4つの遺言書の種類をご紹介したいと思います。
遺言書を作成すべきか考えてる方は「遺言書 書くべき人」を参考までに。
【相続関係のリンク先】
親が亡くなったらすること。手続き 葬儀 相続 相続放棄
遺産分割協議書とは
農地・森林を相続した場合
相続時の不動産調査(市と法務局の相違)
遺産分割をやらないとどうなる?
相続手続き 自分でできる?
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、署名、捺印をして作成する遺言書です。
自筆証書遺言を作成するには、次の要件を満たす必要があります。
- 遺言者本人が全文を自筆で書く
- 作成した日付を正確に自筆で書く
- 氏名を自筆で書き、印鑑を押す
- 訂正は印を押し、欄外にどこを訂正したかを書いて署名し余白部分に「本行に〇字削除〇字加入」といったように記載する
- 財産目録は自筆ではなくパソコンでもOK。通帳や登記事項証明書はコピーの添付でOK。ただし、各ページに自筆による署名と捺印が必要
自筆証書遺言メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①作成に費用が掛からない | ①要件を満たしていないと無効になる |
| ②いつでも手軽に書ける | ②紛失や破棄、書き換えのリスクがある |
| ③遺言の内容が自分以外に知れることがない | ③死後に発見されない場合がある |
| ④死後に裁判所での検認手続きが必要 |
上記表のデメリットである、「②紛失や破棄、書き換えのリスクがある」、「③死後に発見されない場合がある」、「④死後に裁判所での検認手続きが必要」に関しては、現在のある制度を利用することによってこのデメリットを解消することができます。
それが【自筆証書遺言保管制度】です。
この制度は、法務局に保管費用(3,900円)を支払い自筆証書遺言を保管してもらう制度です。
◦保管場所が法務局となるので、②の紛失や破棄、書き換えのリスクが完全になくなります。
◦死後に相続人に通知される仕組みになっているので、③の死後に発見されない場合があるというリスクもなくなります。
◦更に、④の死後に行う家庭裁判所での検認手続きが不要となります。
ですが、「①要件を満たしていないと無効になる」に関しては、申請時に法務局の職員が形式上の不備がないかどうかを確認してくれますが、それはその自筆証書遺言が有効であることを保証するものではないのでデメリットの解消とまでは言い切れません。
また、保管後に氏名や住所の変更があった場合は届け出が必要となります。
法務局のリンク先を貼っておきます。【自筆証書遺言保管制度】
⇩ ⇩ ⇩
公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する遺言書です。
公証人が遺言者が口述で遺言の内容を確認し、その内容を文章にまとめて作成します。
また、公証人の他に証人2名の立会いが必要となります。
公正証書遺言メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①公証人が作成するため、形式不備などで無効になりにくい | ①手続きに時間と費用が掛かる |
| ②原本を公証役場で保管するので、紛失・破棄・改ざんのリスクが無い | ②公証人と証人2名に遺言内容を知られてしまう |
| ③家庭裁判所での検認が不要 | ③作成時に必要書類がある |
| ④口述できれば、作成可能 |
公証人は、元裁判官や元検察官などの法律実務を経験してきた方の中で法務大臣から任命された法律のプロです。
そのため公証人が作成した公正証書遺言は、形式上の不備による遺言の無効がほとんどなく、内容や解釈に関しても争いが起きにくくなっていて、家庭裁判所の検認も不要となります。
原本は公証役場で保管されるので、紛失、破棄、改ざんなどといった心配もなくなります。
また、目が見えなかったり字が書けない状態の方でも、公証人が口述で遺言の内容を確認して作成してくれます。(口がきけない者・耳が聞こえない者に関しても民法第969条の2に特則として明確に記載されているので公正証書遺言を作成することは可能です。)
しかし、デメリットとして費用・内容を知られてしまう・必用書類の収集などが挙げられます。
◦費用に関しては財産によって料金が設定されており、財産が多い人は、費用も多くかかる料金設定となっています。
◦公証人と証人2名が立合うこととなります。ただし以下の者は証人なれません。
◇未成年者
◇推定相続人・受遺者とその配偶者及び直系血族
◇公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
自筆遺言証書とは違い最低3名には内容を知られてしまいます。
◦作成時に必要な書類として、印鑑証明・不動産の登記事項証明書・戸籍謄本・固定資産評価証明書・預金通帳などなど、揃えなければならない書類が多いという点があります。
公正証書遺言の作成の流れ
1・公証役場に連絡し、相談や依頼をする
2・遺言の内容や希望を伝え、公証人と協議する
3・公証人が案を作成する
4・作成者が案を確認する
5・作成日時の調整と証人の選定をおこなう
6・作成当日、公証役場で公正証書の読み聞かせや署名捺印をおこなう
7・作成手続き完了
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者本人が自筆かパソコンかを問わずに作成した遺言書を封筒に入れた状態で公証役場に持参し、公証人と証人2名の立会いのもと、内容を知られることなく遺言書の存在の証明のみを行ってもらい、本人が保管する遺言書です。
秘密証書遺言メリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①内容を秘密にできる | ①内容や形式不備により無効になる可能性がある |
| ②自筆でなくてもOK(パソコン等) | ②費用がかかる |
| ③改ざんや偽造が困難 | ③本人が保管するため、紛失の可能性がある |
| ④破棄された場合、存在は証明できるが、内容を証明できない | |
| ⑤家庭裁判所での検認が必要 |
メリットとしては自筆かどうかは問わず、内容を秘密にできる。改ざんや偽造が難しいという3つです。
デメリットとしては・・・
◦秘密証書遺言は公証人が、遺言書の存在のみを証明するため内容や、形式不備などにより無効になる可能性があります。また、存在のみの証明のため意図的に破棄されてしまった場合、「確かに存在しましたね内容の分からない遺言書が」で終わってしまう可能性もあります。
◦費用に関しては公正証書遺言と違い、財産からの料金を算定できないため一律11,000円となっています。
◦保管方法に関しても遺言者本人が保管をするため、紛失の可能性があります。
◦公証人を介していても家庭裁判所での検認を要するというのもデメリットと言えるでしょう。
秘密証書遺言の作成の流れ
1・遺言内容を考え、手書き若しくはパソコン等で遺言書を作成する
2・遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に署名捺印した印章で、封印する
3・公証役場へ持参し、公証人と証人2名の立会いのもと封筒を提出し遺言書であること、氏名住所を申述する。
4・公証人が封紙に日付と遺言者の申述を記載する
5・遺言者、公証人、証人が封紙に署名捺印する
危急時遺言
危急時遺言とは、遺言者が病気や事故などで死亡の危機に迫られているときに作成できる遺言です。
危急時遺言はさらにいくつかの種類に分かれていて、主に病気や事故などの危急時に作成する「一般危急時遺言」と、船舶が遭難したときに作成する「難船遭難者の遺言」などがあります。
危急時という事で、遺言者が他の遺言方法を選択できないためメリット・デメリットの紹介はありません。
「一般危急時遺言」の作成の流れ
1・立会人となる証人3名以上を集める
2・遺言者が口頭で遺言内容を伝え、証人が筆記する
3・遺言者と他の証人に筆記した内容を読み聞かせる
4・遺言者と証人が内容を確認したら、証人3名が署名押印する
5・遺言書作成後20日以内に遺言者の住所地の家庭裁判所に遺言確認の申し立てを行う
「難船遭難者の遺言」の作成の流れ
1・船舶の遭難により死亡の危機が迫っている
2・証人2名以上を立合わせる
3・遺言者が口頭で遺言内容を伝え、証人が筆記する
4・遺言者と他の証人に筆記した内容を読み聞かせる
5・遺言者と証人が内容を確認したら、証人2名が署名押印する
6・証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に遺言確認の申し立てを行う
その他
〇「伝染病隔離患者の遺言」
警察官1名及び証人1名以上の立会いが必要
〇「在船者の遺言」
船長又は事務員1名及び証人2名以上の立会いが必要
一般危急時遺言は現実的に少なからずありえるかな。とは思いますが、難船遭難者遺言に関しては現実問題どうなのか?という疑問しか浮かんできません。ですが、遺言の種類の1つとして存在しているのでご紹介いたしました。
まとめ
| 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言 法務局保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|---|
| 遺言作成者 | 本人 | 本人 | 公証人 | 本人 |
| 本人の自書 | 必要 | 必要 | 署名以外は不要 | 署名以外は不要 |
| 保管場所 | 本人 | 本人 | 公証役場 | 本人 |
| 証人 | 不要 | 不要 | 2名 | 2名 |
| 内容を知る人 | 本人 | ・本人 ・法務局職員 | ・本人 ・公証人 ・証人2名 | 本人 |
| 偽造・改ざんのリスク | 高い | ほぼ無し | ほば無し | 低い |
| 費用 | 0円 | 3,900円 | 財産により算定 | 一律 1,1000円 |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
私個人的な見解ではありますが、自分の意思表示を正確に不備なく作成できる遺言書として一番お勧めできるのが公正証書遺言です。
一番お勧めできないのが、秘密証書遺言です。デメリットがメリットを上回っています。
せっかく自分の死後いろいろな思いを未来に託して作成する遺言書なので、自分の意思を正確に不備なく有効な遺言にしていきたいですよね。
「遺言書を作成したいけどどうすればいいのかわからない」という方などは、有効な遺言書を作成するためのに専門家にサポートしてもらうのもよいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。皆様の参考になれば幸いです。
⇩ ⇩ ⇩
